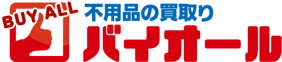日本におけるリサイクルの歴史

江戸は有数のリサイクル都市
日本には「もったいない」という独特の言葉があります。そのせいか、日本におけるリサイクルの歴史は古く、江戸時代は特にリサイクルが発展した時代です。
江戸時代におけるリサイクルとはどのようなものだったのでしょうか?実は、リサイクルを支える業者がたくさんいました。
修繕を商いにする人たち
江戸は人であふれかえると同時に、モノが足りていませんでした。大量生産する技術がまだなく、手作りの品は数が限られたため、壊れたものは直して再利用が当たり前だったのです。そのため、さまざまな修繕業が盛んでした。例えば「瀬戸物焼き接ぎ」は、割れた陶器を白玉粉でつなぎ合わせ、再生させます。骨董品がお好きな方ならご存じでしょう。
次に、時代劇の浪人が行う仕事でおなじみなのが、「古傘買い」です。古傘買いの職人たちは、古くなった傘を下取りし、紙を張り替え、骨を直して新品同様に仕上げます。 そして、防水性のある傘の紙は魚やみそなどを包む包装紙に再利用。折れた骨も燃料にします。
この2つの職業以外にも、大正時代まで存在した「鋳掛屋」や、現代にも残る「研屋」なども存在していました。
不用品買取業者
江戸のリサイクルは修繕だけではありません。不用品を買い取って再利用するリサイクルもありました。
「下肥(しもごえ)買い」は、人の排泄物を買い取って農家に売るか、野菜と交換します。農家が買取った排泄物は作物の肥料になります。
次に紹介するのが「古着屋」です。江戸時代はとにかく着物が貴重品で、武家の女中のボーナスが着物で払われることもありました。ボーナスでもらった着物は高価なものが多かったため、大抵の人が古着屋に出したそうです。
もちろん、新品の着物だけがリサイクルされるわけではありません。 古着屋にも出せないほど着古した着物は子供用になり、端切れは「端切れ屋」に買取ってもらっていました。そして、着古された子供用の着物は、オムツや雑巾に繕い直し、それが使えなくなると、ようやく燃やしたのです。
燃やした灰は「灰買い」が買取ります。灰は洗剤やアク抜きとして売られ、ようやく古着のリサイクルは終了です。
他にも「紙屑買い、紙屑拾い」や「すき髪買い」などたくさんの買取業者がひしめいていました。
「リサイクル」という言葉の始まり
リサイクル大国だった日本が歴史を重ね、現代となって「リサイクル」という言葉が誕生します。 オイルショックの翌年にあたる1974年、元東大教授の糸川博士が命名しました。この頃は、夢の島に大量のハエが発生したこともあり、廃棄物問題が盛んに問われた時代です。そのため、「リサイクル」という言葉は、世間に定着するのにそう時間がかかりませんでした。